木村 暁 准教授(きむら あかつき)

- 新分野創造センター 細胞建築研究室
- 研究テーマ: 核と染色体の細胞建築学/ 細胞内部の小器官や染色体の配置/ 細胞空間のデザイン原理とその力学的な基盤の理解
「細胞建築学」新たな世界観を表現したい
人間工学に基づいて設計された椅子に座り、ロボット工学や建築にも興味がある。
機能を追求したことで生まれるデザインを眺め、どうしてこの形にするといいのか、なぜこの形になったのかと想いを巡らしてきた。木村准教授 が「形」という切り口で生物を見た時、新たな問いが生まれた。
- 形と機能への探究心
 何 がやりたいのかを模索していた大学時代、手に取ったある建築家の本に書かれていたことに興味を持った。「都市は、局所的には個人個人が所有していても、俯 瞰して見ると計画したわけではないのに全体として機能を持っている」。地形に制約があるからこそ、何らかの規定が生まれる。形や空間によって作り出された 秩序や、機能に潜むルールを明らかにしたい。自分が取り組むべき「新たな問題」の匂いがした。
何 がやりたいのかを模索していた大学時代、手に取ったある建築家の本に書かれていたことに興味を持った。「都市は、局所的には個人個人が所有していても、俯 瞰して見ると計画したわけではないのに全体として機能を持っている」。地形に制約があるからこそ、何らかの規定が生まれる。形や空間によって作り出された 秩序や、機能に潜むルールを明らかにしたい。自分が取り組むべき「新たな問題」の匂いがした。- 人間という複雑な生き物もまた、突き詰めて みればひとつひとつの細胞が寄り集まってできている。細胞を形作る分子ひとつひとつの構造や機能に注目が集まる中で、木村准教授は材料の集合体である細胞 の形がどのように決められ、形成されるのかということに着目した。細胞を空間的に組織化された建築物と捉え、どのように細胞小器官が適材適所に配置され機 能を発揮するのか。細胞形成に秘められたデザイン原理や力学を明らかにする「細胞建築学」という新たな学問領域を打ち立て、細胞の形と機能の関係を解き明かそうと試みる。
- 細胞建築学のアプローチ
 細 胞を家に例えるならば、鉄骨にあたる細胞骨格がどのくらいの強度を持つのか。あるいは細胞が分裂する際にどのくらいの力学的負荷がかかるのか。細胞を構成 する個々の分子については、これまでの知見の蓄積がある。だが、全体として捉えたとき「核がなぜ細胞の真ん中にあるのか」という当たり前に感じている現象 の真相が、まだわかっていない。木村准教授はここから細胞建築学の取組みを始めた。
細 胞を家に例えるならば、鉄骨にあたる細胞骨格がどのくらいの強度を持つのか。あるいは細胞が分裂する際にどのくらいの力学的負荷がかかるのか。細胞を構成 する個々の分子については、これまでの知見の蓄積がある。だが、全体として捉えたとき「核がなぜ細胞の真ん中にあるのか」という当たり前に感じている現象 の真相が、まだわかっていない。木村准教授はここから細胞建築学の取組みを始めた。- 仮説をたて、既知の数値を用いてシミュレーションを行 う。そして、実際の細胞の観察と比較することで仮説を実証していく。現在は、核の動向に着目して、しくみに迫る。研究のひとつのゴールは、核だけでなく細 胞の中の動きを全て可視化し、イメージを世界中の研究者と共有することだ。
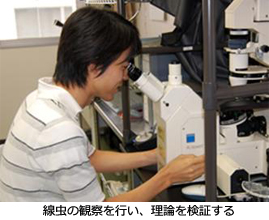 研究姿勢に考え方が現れる
研究姿勢に考え方が現れる- 研究をする上で、問題設定能力と問題解決能力のバランスは重要だ。学生やポスドクが問題設定能力に課題を抱える中、遺伝研は、新たな分野を切り拓く木村准教授の問題設定能力に期待している。
- 「この研究にどんな価値があるのか」。これまでに何度も聞かれた質問だ。医療や健康問題に直結するわかりやすさはない。研究の根源的な魅力である人間の知 的好奇心を満たすこと。そして、自然に秘められた形と機能の関係を、工学へと応用できるかもしれない。
- 「自信なんて最初はないし、今もないですよ。でも自信がつくまで待っていたら何もできない」。勇気を持って自分の意見を発表し、周りから評価をしてもら う。「とんがっていればいるほど、厳しい評価を受ける。けれども、それを受け入れられなければ先には進めないですから」。子どもの頃は、事なかれ主義の優 等生だったという木村准教授に多大な影響を与えたのは大学院時代の恩師だ。「それで、お前はどう考えるんだ」。恩師から常に問われた言葉が、研究の世界で 通用する実力を育ててくれた。どんなテーマを設定し、どんなアプローチをしていくのかというところに、自分なりの考え方が現われる。「最初は無色の自分に、出会った人が様々な色をつけてくれる。どんな人に出会うのかが重要なのかもしれない」。お互い、影響したり、されたりしながら生きている中で、自分な りの世界観を表現していきたいと願う。
- (記事: 株式会社リバネス 2007年インタビュー)















