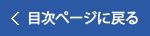角谷 徹仁 教授 ( かくたに てつじ)

- 育種遺伝研究部門 角谷研究室
- 京都大学大学院理学研究科博士課程修了。農水省農業静物研究所、コールドスプリングハーバー研究所、ワシントン大学を経て、2000年より国立遺伝学研究所。 趣味/以後、テニス
植物遺伝学と次代を作る
おもむろに立ち上がり、角谷教授は廊下から研究紹介のポスターを運び入れた。ポスターには、モデル植物のひとつ『シロイヌナズナ』の写真が写る。研究を語る教授の口調はいつもより滑らかだった。
- 自分の研究分野を開拓する
 「今、遺伝学ができていることに非常に満足している」。
現在、角谷教授が取り組んでいるのは様々な特徴を持つシロイヌナズナの突然変異体に着目し、そのメカニズムを明らかにしていくことだ。直接的なDNA の塩基配列の変化だけが突然変異体の原因ではない。「塩基配列情報以外の影響によっても変異体は生じるし、その情報は伝わっていく。DNAやタンパク質の化学修飾はそういった情報のひとつで、その働きがどういうものかを調べている」。数多くの交配を行い、遺伝学的なアプローチで角谷教授はこの謎に迫る。
「今、遺伝学ができていることに非常に満足している」。
現在、角谷教授が取り組んでいるのは様々な特徴を持つシロイヌナズナの突然変異体に着目し、そのメカニズムを明らかにしていくことだ。直接的なDNA の塩基配列の変化だけが突然変異体の原因ではない。「塩基配列情報以外の影響によっても変異体は生じるし、その情報は伝わっていく。DNAやタンパク質の化学修飾はそういった情報のひとつで、その働きがどういうものかを調べている」。数多くの交配を行い、遺伝学的なアプローチで角谷教授はこの謎に迫る。- 「自分がやらなくても誰かが解明してしまうような研究で、速さを競いたくない。それが楽しいとは思えないから。でも、誰もやっていないけれど、そこに気づいてやったら面白い研究はある。それをやろうと日々考えている」。こう考える角谷教授は、論文を読んで思いつく実験よりも自分の研究材料をいろいろいじってみることを大切にしている。そこに、他の人が気づいていない研究の種があると言う。
- 結果の分からない実験ほどおもしろい
- 学生時代は細胞性粘菌を使って形態形成の研究をしていた。だが、遺伝学がやりたくてシロイヌナズナを使った研究を始めた。自分の興味に向かって進み、「自分だけが知っている」世界を作ってきた。
 「できるだけ結果のわからない実験をしたい。一番やる意味のある実験は、Aという結果とBという結果が50%-50%の確率で出ると予想される実験だと思う」。角谷教授は穏やかに、しかしはっきりと言う。もちろん仮説があたったときはうれしい。だが、それ以上に研究をしていてうれしい瞬間があるという。「予想していない結果が出て、その結果を納得できたときはぞくぞくするし、研究が報われたと思う」。最近この瞬間を味わったのは、角谷研究室の研究員が発見した結果だ。「彼女は僕と違って、とにかく実験してみるというタイプ。違うタイプの人がいてくれる ことで、刺激を受けられる」。違う考え方も受け入れる。この柔軟さが新発見の芽を逃さない。
「できるだけ結果のわからない実験をしたい。一番やる意味のある実験は、Aという結果とBという結果が50%-50%の確率で出ると予想される実験だと思う」。角谷教授は穏やかに、しかしはっきりと言う。もちろん仮説があたったときはうれしい。だが、それ以上に研究をしていてうれしい瞬間があるという。「予想していない結果が出て、その結果を納得できたときはぞくぞくするし、研究が報われたと思う」。最近この瞬間を味わったのは、角谷研究室の研究員が発見した結果だ。「彼女は僕と違って、とにかく実験してみるというタイプ。違うタイプの人がいてくれる ことで、刺激を受けられる」。違う考え方も受け入れる。この柔軟さが新発見の芽を逃さない。- ゆっくりと未来の種をまく
 シロイヌナズナは植物の中では一生が短く実験に適したモデル生物とはいえ、次の種を作るまでの一世代が一ヶ月以上かかる。その時間を角谷教授は次の種まきに 当てている。通常の研究室では、このような作業を教授自らやることは稀であるが、研究室の研究員のためにこの地道な作業を今も続ける。
シロイヌナズナは植物の中では一生が短く実験に適したモデル生物とはいえ、次の種を作るまでの一世代が一ヶ月以上かかる。その時間を角谷教授は次の種まきに 当てている。通常の研究室では、このような作業を教授自らやることは稀であるが、研究室の研究員のためにこの地道な作業を今も続ける。- 「アイディアを思いついても即実験というわけにはいかない。だから、材料作りというか、次にすることを用意しておく」。
- 「シロイヌナズナの種まきと交配は私の仕事」。一段大きな声で発せられる言葉に教授の自負心を感じた。
- シロイヌナズナの種に角谷教授は研究と研究員の二つの未来を見ている。
- (記事:株式会社リバネス 2006年インタビュー)